喫茶「城の眼」と高松の建築文化(3) [研究ノート]
2-3.「インダストリー以後の建築」における石壁の可能性
少し前述したが、前川國男にとって1960年代は、彼の作風すなわち建築観が大きく転換した時期であった。1920年代後半にモダニズムの巨匠であるル・コルビュジエに学んだ前川は、戦後、復興へと進む工業化の中で「基礎的な技術の開発と、その共有化への努力」として「「純ラーメン構造(ドミノ)」+マンテル(建物の外皮)」の追求、というテーマ」を掲げ、「日本相互銀行本店」(昭和27年:1952)・「MIDOビル」(昭和29年)・「神奈川県立図書館・音楽堂」(昭和29年)・「岡山県庁舎」(昭和32年)・「日本住宅公団晴海高層アパート」(昭和33年)を生み出していく。このテーマは、コルビュジエの提唱した「近代建築の5原則」の「自由な平面」と「自由な立面」に通ずるものであり、1950年代前半を中心としたこれらの作品は、近代建築の理念を具体化し、日本に定着させる試み(テクニカル・アプローチ)と評価されている(松隈2005)。
しかし早くも1950年代後半には、前川自身がテクニカル・アプローチに対して疑問を抱き始めるようになる。その疑問は、工業製品からなるこれらの建築が時間の経過に耐えることができるのか、もっと言えば古びつつ美しい「廃墟」と化し、街に溶け込むような存在になり得るのか、というところにあった。そしてその答えとして、構造とマンテルに表れた無機質な経済性・合理性の追求から、次第に空間やディテールの洗練、あるいは年月に耐える質感をもつ素材の選択へという方向性が打ち出されていく。この転換は、「岡山美術館」(現・林原美術館、昭和38年:1963)に始まり、「埼玉県立博物館」(昭和46年:1971)・「熊本県立美術館」(昭和 52年:1977)で明確にその姿を現したのである。
転換後のマンテルとしてよく知られるのが、「打ち込みタイル」である。これは、壁体構築時に型枠面にタイルをセットし、背後にコンクリートを流し込む工法で、壁体構築後の仕上げ段階で表面にタイルを貼り付けていた従来の工法とは異なるものである。日本相互銀行の建築には前川による様々な試みがなされたが、打ち込みタイル工法も「砂町支店」(昭和36年)での施工を経た後、「埼玉会館」(昭和41年)で全面的に採用された。この前後の時期には、「京都会館」(昭和35年)で中空レンガ・ブリック、「岡山美術館」で焼過レンガによる組積工法が適用されており、これらも打ち込みタイルへと収斂していく試みと評価されている(松隈2005)。
このような前川の背景を踏まえ、昭和37~39年に施工されたニューヨーク世界博覧会日本館(1号館)の石壁を眺める時、そこには煉瓦→打ち込みタイルとは別の、マンテルへの模索が読み取れる。その工法は、コンクリート壁の外側に積み上げており、壁構造と一体化していない後張工法という点で打ち込みタイルとは異なる。いわば外表(皮膜)としての表現に留まるのであるが、石積みの方が通常のタイル張り工法よりも劣化・剥落の危険性が少ない。近視眼的には、この点に石壁の可能性を考えていたのではないか、とも思える。
ところで、実現した前川の作品を見ると、石積み外壁による量塊感あふれる建築は、この日本館にほぼ限定されると見てよい。このことが日本館を前川作品の中で孤立的な存在にしているのだが、実現しなかったコンペ案を含めると、意外にも戦時中にその先行事例を見出すことができる。
忠霊塔コンペ応募案第1種(昭和14年:1939)と東京市忠霊塔コンペ応募案(昭和17年:1942)は、ともに台形立面で、圧倒的なヴォリュームをもつ石積み外壁が特徴である。特に東京市忠霊塔案は、「塔ではなく、石を積んだ奥津城をつくろうと話した」といい、城郭の石垣がモチーフにされたという(生誕100年・前川建築展実行委員会監修2006)。戦没者の霊を慰め、顕彰することを目的とした忠霊塔という施設に対して前川が抱いたイメージが、城郭石垣であったということは興味深い。
同じ年に前川が書いた「覚え書-建築の傳統と創造について」には、当時の「国民的建築」に関する考えの一端が窺える(前川1942)。そこでは、「我等が傳統を重視するのは、現在に於ける新しき時代の創造的行為者としての立場に立つ限り、(中略)傳統の中にその歴史的地盤を掴みとらねばならず、我々の理念はかくの如き表現的環境を疎外して出生の術を知らぬからである」が、「単なる様式の模写的復興に満足するものは抽象的な伝統主義に過ぎず真に創造への傳統の意味を理解するものとはいへない」としており、明治以来続く洋風の歴史主義建築を否定し、その延長にある所謂「帝冠様式」や、それとは一応対極にあるバウハウス的なモダニズムをも批判している。
前川自身、この覚え書の中で望ましい「国民建築」の具体像を示すことはなかったが、前後の実作・コンペ案から見て、「ダイナミズムや、自然素材の肌ざわりによる実在感」を求めるデザインの体質をもつコルビュジエ的なモダニズム(藤森1993)に、その解を求めていた可能性が高い。あくまで比喩としてではあるが、「覚え書」には素材としての石に関する記述が見られる。「一塊の石材はも早や単なる自然科学的な石でもなく単なる素材的自然としてでもなく、更に表現的自然として『建築へ働きかける声なき意志』として已に作られたる者の性格を備へてゐる」。素材自身がその存在を主張するような伝統的表現として、モニュメントとしての城郭石垣というモチーフが選ばれたのではなかろうか。
ところが同年、前川らが審査員を務めた大東亜建設記念造営計画において1等当選は果たした、丹下健三による大東亜建設忠霊神域計画では、コンクリート打ち放しによる、伊勢神宮を通じた家形埴輪への接近が図られている。
ここに、外壁の表現に対する前川と丹下の根源的な志向の違いを見出すことができる。すなわち、素材は様々だが建築の構造とは別の形(後張り工法等)に依拠してマンテルというテーマを掲げた前川と、構造部分の連続的な外皮という形でコンクリート打ち放しを前面に掲げた丹下、という対照的な志向である。この志向は、戦後の1950年代いっぱいまで続き、前川がほぼ全面コンクリート打ち放しの外壁に取り組むのは、世田谷区民公会堂(昭和34年:1959)から弘前市民会館(昭和39年:1964)までの僅か5年間である。そして重複するが、前川が再びマンテルへと取り組む1960年代前半に日本館が位置しているのである。
世界博覧会日本館という場において、「日本」という枠組みの提示が求められた時、前川が強く意識したのは工業ではなく、それにより蝕まれる日本の風土であった(前川1965)。その問題意識は、同時期に前川自身が抱えていた問題機制-工業製品ではない新たなマンテルへの模索-と完全に一致する。一方は戦争という外に対する創造的伝統、そしてもう一方は工業化という内に対する風土の問題としてではあるが、戦時中と1960年代前半の前川を巡る背景に重なる部分があると見るのは、あながち的外れな見方ではなかろう。そのような意味で、石積み外壁という建築表現は、伝統・風土に対する前川の意識と、本質的にもっていたマンテルへの志向の原点を現すものなのではないか。同時に日本館の石壁に、流政之と庵治・石匠塾による芸術的かつ職人的な表情が加えられたのは、日本の工業化社会に対する危惧が含意されているようにも見受けられる。


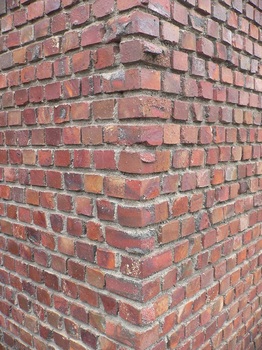





コメント 0